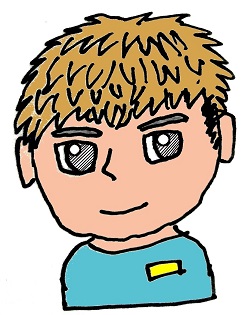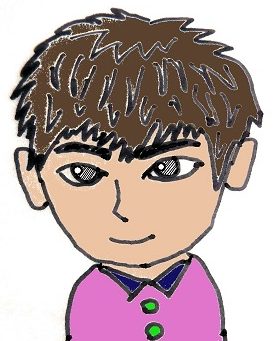生活していくと物がどんどん増えていきますよね。
子供がいる家庭ならなおさらです。
物は増えても、家の収納には限りがあって困りますよね?
断捨離出来ればいいのですが、成長盛りの子供がいる家庭は物が増えていく一方です。
そんな時は、DIYで自分の家の空きスペースを有効に利用した棚を作ってみましょう。
空いているスペースは家ごとや部屋ごとに違うので、家具屋さんには売っていません。
オーダーメイドという手もありますが、お値段が高くなりそうです。
ということで、今回は部屋の入り口にあるドアの開閉スペース(廊下側)を利用した棚をDIYで自作したいと思います。
なぜドアの開閉スペースに棚を作るか?
普通は部屋の中に棚を作りますが今回はドアの開閉スペース、つまり廊下側に棚を作ります。引っ越し先や新築なら話は別ですが、すでに何年も住んでいる場合は部屋のレイアウトは急に変えられません。そこで、僕は部屋の中ではなく収納の無い廊下側に作ろうと考えたわけです。以下は、僕なりに考えたQ&Aです。
部屋の中の方に棚を作ったほうがいいのでは?
部屋の中は既に居住スペースがあるから新たに棚を追加するのは大変ですが、子供の塾のカバン等の小物を置くなら廊下側でも問題ないはずです。
なんでドア裏に棚を作るの?
そもそもドアを開けるためだけのスペースというのがもったいないと思います。ドア1枚分の可動範囲はかなり広いので、このスペースを利用しない手はないですよ。
ドアを開けると棚板にぶつからない?
棚板がドアにぶつからないようにL字にカットすればOKです。ドアと干渉しない部分には大きいものが置けますし、ドアと干渉する部分には普段あまり使わない小物を置けますね。
家を傷つけたくないんだけど大丈夫?
ラブリコアジャスターを使えば家に傷をつけずに棚を作れます。釘やビスで柱板を固定しないので、別のドア裏スペースに棚を引っ越しするときも楽ですよ。
床と天井には巾木があるから、棚が壁にぴったりつけられないよ?
普段は床や天井部分は見ることがありませんが、壁を保護する為に巾木がついています。
この柱板の巾木と重なる部分をL字にカットすれば、壁にぴったり付けられます。
これなら棚を作れそうですね。では実際に棚を作る手順を説明しますね。
設置場所の寸法を計測する
これが個人的に一番大切なポイントだと思います。棚を置きたい場所の寸法が正しくなければ、今から作る棚が設置できないという事になります。
例えば床から天井までの棚を作る場合には床から天井までの寸法を測りますが、棚は左右の柱となる木材が床から天井までの寸法よりも長かったら設置できません。左右の柱を置く場所それぞれの、床から天井までの寸法を測りましょう。
縦の寸法を測ったら、横の寸法も図りましょう。これで設置できる棚の大きさがだいたいわかりますね。今回は、部屋に入るドアの反対側の壁にぴったりの棚を作りたいと思います。
イメージとしてはこちらになります。(すみません、wordで書いた絵です。)
 棚の設置場所のイメージ図
棚の設置場所のイメージ図作りたい棚のだいたいの設計図を書きましょう
設置場所と作りたい棚がイメージできたら、簡単に設計図を書きましょう。ここで購入する木材の数とサイズが決まります。そんなに細かくなくてもいいのですが、木材が足りない~なんて事になると何度も買いに行かなきゃならないので面倒です。
買い物は1回で済ませたいので、それなりに書きましょう。
これで必要な木材のサイズと本数が決まりました。
| 右側の柱の木 サイズ:1×4インチ 長さ:床から天井まで高さ – 75mm(*1) 1本 |
| 左側の柱の木 サイズ:1×6インチ 長さ:床から天井まで高さ – 75m(*1) 1本 |
| 棚の木 サイズ:1×6インチ 長さ:棚の幅 5本 |
(*1):ラブリコアジャスターを使用するので、柱木の長さは75mm短くしてあります
左右の柱の木のサイズが違うことにお気づきでしょうか?
右側は1×4に対して、左側が1×6になっています。
これは、ドアの可動範囲を考慮して右側の幅を4インチにしてあります。
左側はドアの可動範囲外なので6インチでも大丈夫ですが、右側はドアの可動範囲に入ってしまうので棚にぶつかってしまいます。
これを防ぐために、下の絵のように棚板はカットする必要があります。
 棚板がドアの可動部にぶつからないようにカットします
棚板がドアの可動部にぶつからないようにカットします全ての板を1×6で作ってもいいのですが、棚板をカットする必要があるので右側は1×4にしたというわけです。
さて木材のサイズと数は決まったので、次は金具類ですね。
天井までの棚を作るので、ラブリコの1×4アジャスターを使って天井と側で固定します。
真ん中の位置の棚板は強度を持たせるために金具で固定するので、L字金具2個とビスが必要です。その他の棚板は可動式にしたいので、ダボ金具で固定するようにします。
1枚の棚板を4個のダボ金具で固定しますので、棚板の枚数x4個が必要ですね。
| ラブリコ1×4アジャスター: 2個 |
| L字金具: 2個 |
| ビス: 1セット |
| ダボ金具: 3セット |
ホームセンター等で木材と材料を購入する
いよいよホームセンターでの購入となります。
ここで気を付けたいのが、木材を家まで運ぶ手段です。
天井までの長さの木材となるとかなり長いので、車で運ぶことになると思います。
1BOXの車なら問題ありませんが、軽自動車のサイズだと厳しいかもしれません。
ホームセンターによっては軽トラックを貸し出しサービルがあるかもしれませんので、
必要に応じて利用しましょう。
木材ですがSPF材を利用すると思いますが、微妙に反ってたりヤニが出ているものがあるので慎重に選びましょう。購入の際は必ず、ホームセンターでカットしてもらいましょう。
1カット数百円の有料になるかもしれませんが、家で切るよりも絶対に楽ですのでカットしてもらいましょう。
木材のほかにも、先ほど調べたラブリコアジャスターや金具類も購入します。
木材を加工する
5-1. 柱板の巾木を重なる部分をカットする
柱板は壁にぴったりつけたいのですが、壁の床側には巾木(はばき)がついているので、このままでは無理です。巾木とは、壁と床の接点を保護する部品です。
巾木に沿って柱を立てると、柱と壁に隙間ができてしまいます。
僕はこれがどうしても気になってしまったので、サンダーという道具を使って柱板の巾木が当たる部分をカットしました。
柱板をL字にカットして巾木をまたぐようにすれば、壁にぴったりつけられますよ。
 マークした部分が巾木の位置です
マークした部分が巾木の位置です
5-2. 棚板のドアの可動部分をカットする
棚板はそのままだとドアを開けるとぶつかってしまうので、可動部をカットします。
これもサンダーという道具でカットしました。サンダーは手軽にカットできるのですが、
垂直で真っすぐに切るのが難しいです。多少ずれたりしますが、手作りという事で気にしないことにしました。
5-3. 木材のやすり掛け
木材の加工が終わりましたら、やすり掛けしてすべすべにしましょう。
まずは手袋をはめてから、200~320番の紙やすりを使ってひたすら磨きましょう。
時間をかけた分だけきれいな仕上がりになりますが、とても時間がかかります。
ここは素直に電動サンダーの導入を検討すべきかと思います。
かなり大変な作業で僕は苦手なのですが、子供が触ってトゲがささらないように
しっかりやすり掛けすることが大切ですよ。
5-4. 木材の塗装
これは別にしなくてもいい作業です。僕は壁紙が白色だったので棚も白色がいいなと思って塗装しましたが、好みの問題ですね。木の色がいい場合はそのままでも問題ありません。屋外でしたら油性ニスでもいいのですが、家の中で子供用の棚なので水性ニスを使用しまた。
めんどうなら塗装しなくてもOKです。塗装するなら水性ニスがおすすめです。
5-5. 棚板のダボ穴をあける
棚板は可動式にしたいので、固定用のダボ金具を差し込む穴をあけます。木工用ドリルを電動ドリルドライバーに取り付けて、10cm間隔でダボ穴をあけました。
この穴あけは必ず木工用ドリルを使ってください。鉄工用ドリルで穴をあけてしまうとバリだらけになってしまい、穴あけよりもバリ取りの方が大変な作業なってしまいます。
僕の経験談ですが、必ず木工用ドリルで穴をあけてください。鉄工用ドリルを使うとバリが量産されます。
設置場所で棚を組み立てる
いよいよ最後の組み立てとなります。今までのコツコツとした木材の作業は地味で目立ちませんが、組み立てて立派な棚になったら、子供も奥さんも「おおっ」と目を見張ると思いますよ。
6-1. 柱板にラブリコアジャスターを取り付ける
柱板の上の部分に柱板にラブリコアジャスターを取り付けます。ここで注意したいのが、巾木の幅です。先ほどの巾木ですが、何と天井にもあります。ラブリコアジャスターを取り付ける際には、巾木のサイズ分、ずらす必要があります。
 ラブリコ上部をずらして取り付けます
ラブリコ上部をずらして取り付けます
1×6の柱板では問題ありませんが、1×4の柱板ではラブリコが少しはみ出てしまいます。
まぁ、そうそう天井を見上げるものではないと思うので、これでよしとしました。
柱板の底の部分には、ラブリコ付属のマットを貼り付けます。
6-2. 柱板を固定する
まずは右側の柱板から固定します。ラブリコの上部を抑えながらクランプを閉めて固定します。次に左側の柱板を固定します。こちらは仮止め程度にしておきます。棚板を下側、中央、上側と順に合わせていき、棚の幅を調整してから左側の柱板を固定します。
6-3. 棚板を設置する
DIY棚の完成はもうすぐです。棚の真ん中部分に棚板をL字金具で固定しましょう。全ての棚板を可動式にしてしまうと棚の強度に不安がありますので、真ん中部分の1か所は固定しておきましょう。
強度を出すために、中央の棚板はL字金具で固定します。
残りの棚は置きたい物のサイズによって、ダボ金具を穴に差し込んで棚板を置けばOKです。だたこれだけでは棚板がダボ金具の上に乗っているだけの状態ですので、手前にズレてしまいます。そこで、棚板の位置が決まったら裏側を見てダボ金具の部分にマークをして、この部分を彫刻刀でくり抜きます。これにより、ダボ金具がくり抜いた部分にはまってズレにくくなります。残りの4枚の棚板も同様に設置しましょう。
 棚板を設置しました
棚板を設置しました
 ドアを開閉しても棚板にぶつかりません
ドアを開閉しても棚板にぶつかりません6-4.棚板がずれないように固定する
完成したかに見えるDIY棚ですが、棚板の左右の幅が違うのでバランスが悪いです。
棚板のL字付近に重いものを置くと、棚板が前にひっくり返って物が落ちてしまいます。4
 棚板がひっくり返ってしまいます
棚板がひっくり返ってしまいますこれを防ぐために棚板に転落防止のストッパーを付けます。
ストッパーとして使うのは「画鋲」です。今回は棚を白色に塗装したので目立たないように透明な画鋲にしました。この画鋲を、左側の棚柱に取り付けます。画鋲の持ち手の部分がストッパーになるイメージです。
 棚板の転落防止に画鋲を使います
棚板の転落防止に画鋲を使います 画鋲がストッパーになっています
画鋲がストッパーになっています全ての棚板に画鋲のストッパーを設置すれば完成です!!
まとめ
ドア裏のスペースを利用した収納棚を、DIYで作成する手順を説明しました。この作り方なら、ドアを開閉しても棚板にぶつからずに収納スペースを増やせます。我が家では、この棚に子供用品を置いています。子供が出かける時に、ドアを開けてそのままバックを持って塾に行くことができるのでとても便利に使っているようです。
この記事を読んで、DIYを始めようとしている方々の手助けになれば幸いです。
また、子供と一緒にDIYを始めるのなら、子供の安全を優先させてください。
子供が怪我をしないように安全第一に、そして子供の勇気を尊重しながら一緒に作っていく・・・ちょっと難しいですが、親子で同じ目標を達成することは子供にとって貴重な経験だと思います。